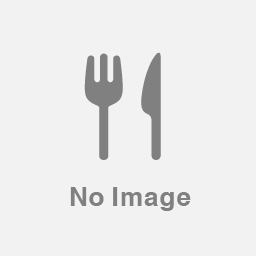ぴあの(2005年6月)
交通事故でジャズ奏者の父親をなくして、ジャズピアニストの母親と二人暮らしの片腕の少年と、ある夏、めぐりあう気の強い美少女とその弟の話である。交通事故で片腕をなくした少年のピアノと、美貌の母親とそのピアノに対する想いをめぐる物語だ。物語の背後にはいつもジャズピアノが低く響いている。
音楽をめぐる物語が好きだ。昔から音楽が好きだったからだろう。
母親の音楽への愛情と果たせなかった夢への代償のように、はじめたピアノ。父親は喜ばなかった。1960年代という時代が、男がピアノを弾くということに対して持っていた違和感が、父親の反応に反映していた。中学ごろまでは音楽大学をそれなりに、真剣に考えていた節がある。ただ小学校の高学年の頃から入り込んできたギターという楽器が、ぼくの音楽生活をどんどん趣味の方向へと変えていった。
ジャズに対する畏敬が生まれてきたのはいつ頃だったろう。
北国の古い港町で小学校に行っていた頃、父親が書斎の半分を占めるような大きなステレオを買ってきた。その後ベストアルバムをよく買ってきた。ブラザースフォア、ジョーン・バエズ、そしてマイルス・ディビス。そのあたりに発端はありそうだが、中学の頃から若干ませ気味に読みはじめていた五木寛之の小説の影響もあるだろう。「青年は荒野をめざす」「デラシネの歌」「内灘夫人」などには、まぎれもなくジャズの音が響いていた。
ジャズをめぐる記憶を手繰っていって次にいきあたる光景は、1970年代前半の古い貿易港だ。ぼくはこの街のプロテスタント系の私立高校に通う17歳だった。ぼくはバリトンの声をかわれて、グリークラブに入団していた。男声合唱の分野ではそれなりに知られた伝統のあるクラブだった。

そのクラブのスノビッシュな雰囲気が、当時庄司薫の青春小説に展開される、高校生活に憧憬の念を抱いているような少年を集めるようになっていて、一種独特の、高校というよりは私立大学のような雰囲気があった。ぼくのジャズをめぐる記憶は、クラブの合宿だ。毎年、全国大会をめざし、まるで体育会的にストイックな練習を続けていて、冬休みには恒例の冬合宿があった。高台にある元外国の領事館の建物で、昔はその国の領事がジャム入りの紅茶でも飲みながら、窓の外に広がる港の風景に見とれていたダイニングルーム跡のホールの片隅に、古ぼけたレコードプレーヤーがあった。
ぼくの一級上にMという大人びた少年がいた。Mの兄貴もこの高校の卒業生だった。彼は、ジャズフェスティバルなどが開催されている洒落た街の中学の出身だった。Mの兄は大学を卒業した後、プロのジャズピアニストになり、新宿のピットインなどで演奏するようになっていた。
Mが大事そうに一枚のレコードを取り出して、プレーヤーにのせ、針を落とした。数人の少年は文字通り息をつめて、まるで、聖なる儀式をみつめる信者の風情で、天上の音の到来をまちわびていた。これまで聞いたジャズの音の塊とは違った、リリカルなピアノの響きがそこにはあった。Mが持っているカバーにはチック・コリアという名前が印刷されていた。ホールの暗い照明のしたで、石油ストーブの紅い炎に包まれ、皆あたりを気遣うように小声で話しながら、その新しい音の連なりにひたっていた。
Return To Forever (Chick Corea, Stanley Clarke, Al Di Meola, Lenny White) - Jazzaldia Festival 2008
次の光景は、1970年代の東北の大都市へ移る。ぼくは20代の大学生だ。少年の頃の音楽大学は、現実という中でなし崩し的に消えていき、当然自分の中にも音楽と心中するというものがあったわけでもなく、さしたる断念もなく法学部という見事に現実的衣装を身にまとうようになっていた。法律という現実と20代という情緒とのあいだでかぎりなく不安定だった。そんなギャップを埋めたのがジャズだった。
一番町という繁華街の一本路地に入ったところに、その小さなジャズ喫茶があった。カウントという看板がかかっていた。中国人のようなマスターと職人風の若い男が、切り盛りしている店だった。ファッション化して、そのうちにアイデンティティがなくなって潰れてしまった東京のジャズ喫茶とは違って、徹頭徹尾、地下室的な意固地さが蔓延している空間だった。ただ客層は学生ばかりじゃなかった。

店に備え付けの落書き帖には果し合いのようなジャズ評論が書きなぐられていた。自分が何かを書いたあとに、誰かがそのノートを読みはじめるときの胸騒ぎのような気持ちは、いまでも忘れられない。ぼくはそこに通いつめて、ジャズファンというものの、行儀作法の一式を教わった。ソニー・クリスのクリスクラフトというぼくにとっての名盤にであったのもこの店だった。薄暗いカウンターでコーヒー一杯でねばりながら、文庫本を読むなどという昔なつかしい大学生を演じさせてもらった。倉橋由美子の「暗い旅」を読んだのも、この店のカウンターだったし、その中にでていた京都のシアンクレールというジャズ喫茶めあての旅を、することにもなった。
ピアノとジャズをめぐる記憶はここから、一足とびにに90年代のニューヨークに飛ぶ。ぼくは30代後半の二人の子持ちの金融マンだった。ニューヨークとはいってもブルーノートとか、スイートベージルのおもいでじゃない。ラジオをひねると一日中ジャズが流れている局があったり、映画のBGMにもジャズが多い。ジャズはニューヨークの空気の中にみちている。しかしぼくのニューヨーク的ジャズの記憶はそこにはない。
妻が突然ピアノをはじめたいと言いだした。
ぼくたちの住んでいた街には、同じような環境の駐在員が多かった。学歴も境遇もきわめて似通った人種が集まっている。彼らは似たような少年少女時代をおくって、似たような青年時代をおくり、これまた似たような断念をして、この異郷にいる。そんな類似した境遇の中でも、ピアノをめぐる思い出を共有する人々は意外に多かった。

皆どこかでピアノをはじめ、一度は音楽大学を目指し、同じく軽い断念とともに、ピアノを捨てている。そして社会の中でそれなりに努力し十数年働き、あるいは家事に没頭し、ふっと自分というものをふりかえるときに、断念の軽さのゆえに、ピアノをめぐる記憶が奔出するようなのだ。いわば、ピアノというものが自分がありえたかもしれない素敵なもの、心踊るすべてのものを、集約的にあらわすとでもいうかのように、ピアノへの想いが強まるのだ。
日本人が教えるピアノスクールに、妻は隣人たちと通うようになった。ロバート・ペースという教師が作った、Cという特定の音階中心主義を相対化する試みだった。それと同時に、古典音楽を時系列的に辿るのではなく、存在する音楽を横に並列して、現代音楽と古典音楽が共存している。ヘンデルとバルトークやさらに現代的な音楽家の作品が、ひとつの練習曲集に並存している。戯れに弾いてみた曲想の新しさにぼくの中でも、かつてありえたかも知れない自分が、ピアノという形で甦ってきた。そしてぼくも土曜の午後に子供や主婦にまじって、ジュリアードに通っている若い教師から、ピアノレッスンを受けることになった。
ぼくは練習曲として、ドビュッシーのベルがマスク組曲の序曲をもらった。まるで音楽大学というコトバがそれなりに重大な響きを持っていた中学生や、モダンジャズという秘教めいた響きに憧れた高校生の、ぼくが帰ってきたようだった。練習がすすむにつれてぼくはわがままをいい、ビル・エバンスの採録譜を買ってきて、ワルツ・フォー・デビーの練習を始めた。ハドソン川沿いの町で、若いピアノ教師の視線に晒されて練習したビル・エバンスがぼくにとってのもっともニューヨーク的なピアノの記憶だ。
ピアノの天性を持ちながら、事故という形でその天命の宿る片腕を失った少年と、彼の右手が奏でるサマータイムのメロディーに、運命的に吸い寄せられる姉弟の物語は、ぼくの中でガーシュインの旋律を基調低音として、散乱していた記憶の破片をひとつづきの物語の形によせあつめた。ぼくや、ぼくと同じ時代を生きてきた多くの普通の人々のありえたかも知れない自分とその断念、あるいは失われた片腕へのかすかな後悔と郷愁がピアノというコトバに集約される形で僕の物語を呼び寄せた。