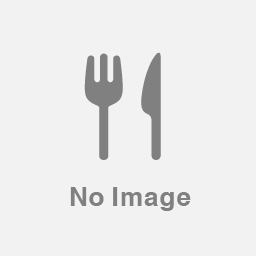教えるということ、学ぶということ(2005年6月)
ぼくの父親は、社会科の教師だった。大正生まれで、第二次世界大戦に徴兵され、満州などを陸軍の兵隊として転戦し、敗戦を迎えた。戦後の変革の中で、教員組合運動に従事し、地域の教員組合の委員長をつとめた。60年安保の頃には、岩波の「世界」を購読しているというだけで、警察の内偵があったと言う。その後、管理職となり、組合運動で混乱している学校を中心に転勤した。「毒をもって毒を制す」ようなつもりだったんだろうと、父はのちに苦笑した。

子の買いかぶりをぬいたとしても、父親は、良い教師だった。ぼくの良い教師の定義は一つだけである。自分自身が学び続けていることだ。父親は、7人兄弟の長男で、早くに父親をなくし、彼の給料によって、大家族を支えなければならなかった。彼は、ジャーナリストや弁護士に憧れていた。しかし裕福ではない家計では、師範学校が精一杯だった。そういった鬱屈もかかえながら、彼は教師という道を選んだ。
大学出ではない劣等感を梃子に、父親は大変な読書家となった。大量に本を読み、日記も含め、大量に文章を書いた。そんな父親が本を読むところや、父親の大きな本棚を見ながらぼくは大きくなった。その意味で、ぼくにとっての最初で、一番大切な先生は父親だった。その後も、何人かの重要な師匠に出会った。それは、自分はこの世に何のために生まれてきたのか、自分は何をすべきなのかと悩みつづける過程でだった。ぼくは、正直、先生にめぐまれてきた。
池波正太郎の人気小説「剣客商売」(新潮文庫)にこんな場面がある。
秋山小兵衛は、鐘ヶ淵の隠宅の裏手で、薪を割っていた。風もなく、あたたかに晴れわたった冬の午後である。石の上に腰をおろした小兵衛は、まるで、鋏で紙を切るように薪を割っていた。巻き割りを持つ小兵衛の手がうごかぬほどにうごいている。薪割りの刃が軽くふれただけで、薪が二つに割れ四つに割れてゆくのだ。
剣術一筋の小柄で粋な小兵衛と息子の大治郎が田沼意次の権勢華やかりし頃の江戸を舞台に活躍する人気シリーズだ。めっぽう強く、洒脱な小兵衛には現実のモデルがいた。それが、「又五郎の春秋」という池波正太郎の著作の中でも少々異色な作品の主人公、歌舞伎界の名優、中村又五郎だ。
この魅力的な人物評伝のなかでも、とりわけ、歌舞伎の未来を案ずる又五郎が渾身の力を振るう後進の教育の件りがいい。 魅力ある師匠とは何か。
又五郎が剣客商売の舞台で、その当時、新進だった真木洋子が井戸水をくみ上げる演技を教えるところ。
いうまでもなく、舞台の井戸には水が入っていない。底も浅い。わずか一メートルほどなのだ。その底は板である。
(中略)
「ほらね。こうするのだ」 たちまちに、して見せた。
先ず、縄を撓めておいて、井戸の中を見込み、釣瓶を落す。釣瓶はすぐに一メートル下の板の上へ腰を据えてしまうのだが、又五郎の手に撓められた縄はするすると下へ伸びて行き、井戸の底の深さを観客に納得させずにはおかない。
それから、水が入った釣瓶を引き上げる。
このときも、縄を手繰る手さばきと眼のうごきと、姿勢によって、水が入ったように釣瓶の重さを表現しなくてはならぬ。
歌舞伎の舞台で鍛え上げられた、肉体が語る豊富なコトバ、イマジネーションが池波の筆力によって再現される。芸と芸がぶつかりあう音が行間から聞こえてくる。
又五郎が心血を注いだものに、国立劇場・歌舞伎俳優研修所における「素人」研修がある。
歌舞伎を見たこともない連中を、歌舞伎俳優に仕立て上げるという気の遠くなるような仕事。
初回に、六代目菊五郎や先代吉衛門の話をしても、ポカンとしている若者たちに、又五郎は、実演を交えて教え始める。女形のセリフのいいかたや歩き方、立ち役の仕種などを演じ分ける。と、俄然若者たちの反応が変わり、どよめきが生まれ、眼に必死さがみなぎり始める。
「いつまでたったらセリフをおぼえるんだ!!」
「おまえのおかげで稽古が遅れるんだよ、わかったか!!」
怒鳴りつけておいて
「そうだろう」
の一言に、無限の優しさがこもっている。
昨今、教育論がやかましい。教育とはつきつめれば、自分にとって一番大切なものを見つけるための技術論のはずだ。一見簡単そうだが、好きなものを見つけ出すというのは、案外厄介だ。好きなものが本当に大切なものに変わるためには、その好きであることが持続しなければならないからだ。研修所の若者たちは、幸福だ。目の前で、自分の大切なものを一筋に貫いてきた人生が、血や、息や、筋肉の律動となって踊っていて、又五郎の一つ一つの動きが、自分の人生を生きるということの明瞭なイメージとして記憶に焼きついたはずだからだ。
彼もまた、真剣な教師だったぼくの父親が、繰り返し言った言葉を思い出した。
自分が学びつづけられるものにしか、他人を教えることなどできない。
父親の言葉だけが記憶に残っているわけじゃない。書斎で日記を書く背中、長椅子で寝転んで、ペンシル片手に本を読む姿。胸に本をおいて昼寝している様子。書物を大切するように、薄く引かれた傍線と書き込み。
そんな細かなことが鮮明に残り、父親という存在の輪郭を作っている。
そして、その描写はそっくりそのまま、今の自分の姿だ。
本を読んでいる姿がお父さんそっくりになってきたわね、と妻が横でつぶやいている。
時には父のない子のように(2005年6月)
今年の誕生日に、父親からの祝いの電話はこなかった。
几帳面な父親は、ぼくたちが海外にいた期間も、前日の夜か当日の朝に、誕生日を祝う電話をかけてきた。家族たちも、父親のこういった几帳面さと正確さにいつも感嘆していた。そもそもが、几帳面な人ではあったが、そういった正確さを保つためのシステムを一切持たなかったわけでもない。
葬儀が終わり、父親の書斎を片づけていた。父親は若い頃から大量の日記を残している。特に、ぼくが海外赴任をしていた20年前ぐらいから、5年日記をつけている。1ページに5年分のその日があるのだ。その意味で、誰かの誕生日を、ページの上に書きこんでおけば、5年間、その日を忘れることはない。とにかく用意周到な人だった。
彼はその周到さで自分の喪の準備を数十年間続けていた。
ここ最近のぼくとの対話のほとんどは、自分たちの終わりについての準備の話だった。70代くらいから、そんな会話の頻度は高くなってはいたが、母親が倒れたり入院したり、自分の肺の状態が弱ってきてからは、その切実さは増した。
書斎にあった黒塗りの立派なノートに、喪の準備として、密葬にせよ、院号はいらないと書きこんであったが、そのあとは、白紙のままだった。
急逝した日の前日も、普通と変わらず、ぼくや自分の妹や弟(ぼくの叔母や叔父)と、携帯電話で話していた。最後の日の日記には、体調が少し良くなっているようだと書きこんでいる。
最期の日も、いつもどおり早朝に起きて、居間の暖房を入れ、書斎のカーテンを開けたらしい。当日も、冷えこんだ冬の朝で、そんな冷気の中で、持病の肺気腫からくる呼吸不全を起こしたらしい。あわてて吸入器をもって、寝室へ戻り、そこで倒れ、息をひきとった。しかし、これは、あくまでも想像だ。死に目に会えなかったぼくや家族は、皆で、父親の日々の暮らしのパターンを思い出しながら、最期の瞬間を想像するしかなかった。ただ父親が、最後の朝も、いつものように几帳面に時間通りに生活を開始し、母への見舞いに行く準備の途中で倒れたという想像は、なぜか、ぼくたちの心をあたたかくさせた。
ただ、一人で死なせてしまったという悔いだけはどうにもならない。
父親は、ぼくとの喪の準備の手順どおり、彼の望みである自分の家で、延命用の管などにがんじがらめにされることもなく、卒然と自分の人生を終えた。
その手順どおりがぼくにはつらい。
父親は最期の日々においても、引退後の数十年、くりかえしたリズムを一切崩すことはなかった。
親族、皆で、葬儀場へ向かうマイクロバスに乗りかけた時に、電話がなった。地元のなじみの本屋が、大手チェーンに押されて店を閉めたあと、しばしの落胆の後に、ようやく、見つけ、つきあい得る、と決めた書店からの電話だった。予約の本が届きました。
葬儀が終わったあと、書店で、受け取ったのはカレル・チャペックの本と、太平洋戦争に参加した兵士の本だった。ああこれが、父親が最期に予約した本だ。
その翌週、また電話がなった。同じ本屋だった。予約した本が届きましたという知らせだった。
書店の店頭で受け取ったのは、佐藤正午の「豚を盗む」というエッセイ集。店員に、あと予約しているものはありますかと聞くと、若い女性の店員がていねいに
「これで全部です。」
父親は、日がな、書斎で読書をし、昼寝をし、母を見舞いがてら、書店へ立ち寄るという生活をくりかえした。
葬儀が終わり、49日が終わりと、喪の儀式を経る中でも、父親の死という現実への実感がどこか希薄だ。父親は忽然と天空に消えてしまった。
もともと離れて暮らしていたわけで、週何回かの電話がなくなったということぐらいが現実の違いだ。
父親がいなくなったということが、ぼくの精神にどう影響を与えるのかをいまのところじっと観察している。耳をすまして、神経をはりめぐらせて、ぼくに、起こったのは一体何なのかを思っている。
いつもならかかってくる父からの電話がないこと。それが、最初の喪失感だった。
言葉が舞う(2005年10月)
何年前のことだったろうか、山手線の中で、「言葉が舞う」のを、見た。
電車が、駅にとまると、多くの少年、少女が、乗りこんできた。ぼくは、読みさしの本から眼をあげた。中学生ぐらいの子供たちだった。14,5歳の少年たちが醸し出す、過剰なエネルギーが感じられた。

しばらく、本の活字を追っていったが、ある違和感があった。当然、そういった年代の子供たちが乗り込んでくるのだから、一定の騒音を想定していた。ところが、気配の活発さのわりに、予想した騒音はない。
ぼくは、本から眼を上げた。
そこには、笑いさざめく、年相応の少年、少女の明るい笑顔があった。ただ、一つ、違っていたのが、彼らは、自分の言葉を、手話というテクノロジーにのせて飛ばしていたことだ。
それは、まるで、モダンダンスのようだった。子供たちは、手や指や身体をすべて使って、言葉を相手方に放り投げていた。電車という空間の中で、過剰な言葉が、活発に飛び交っていた。その場面の、音の欠落を沈黙という言葉にあてはめるのは、適当ではない気がした。
ぼくは、しばらく陶然と、その若々しい群舞に見とれていた。
手話という人間のテクノロジーの美しさを認識した、最初の時だった。
次に、ぼくが、手話というものと出会ったのは、Children of the Lesser Godsという聾唖者の女性と、聾唖学校の教師のラブストーリーだった。美しい聾唖者の女優の手話がとても美しい映画だった。
「手話ができるって知ってた。」と、妻が言う。娘のことだ。中高一貫の女子高に通っている。子供の頃から、ダンス、演劇(どちらかといえば裏方)、デッサンなどの表現の方を好む子だった。今は、美大を目指して、都内の美術予備校のようなところに通っている。
「予備校に、耳の聞こえない男の子の同級生が入ってきたんだって。その予備校でも、年に一人か二人そういうケースがあるんだけれど、なかなか、個別対応が難しくて、学校側も困っていたらしいのよ。」
ところが、学科については、そんなに目立つ方ではなかった彼女が、新入生と突如手話で話しだしたというのである。新入生も、先生方もびっくりしたらしい。
「まわりに、耳の聞こえない人がいるの」って聞かれたわ、と娘は言う。いないというと、それなのに、手話ができるのはとても珍しいと言われたらしい。
娘が小学生の時に、耳の聞こえない薄幸の少女が主人公のテレビドラマがあって、その中で、主題歌を手話で表現するところがあった。娘は、学芸会で、その手話と歌を演じた。
その後も、彼女が、手話についての関心を持ち続けていたことを、ぼくたちは知らなかったし、彼女の手話のレベルが、美術学校の技術についての説明が翻訳できるレベルにあるなどと思いもしなかった。
以来、彼女は、美術学校の先生からも、新しいクラスメートからも重宝され、ありがたがられている。外国語は外国人と話すことによって上達するのだから、新しい言語である手話も日々の生活の中で利用する機会が多ければ多いほどよいに決まっている。
娘は、子供の頃から、コミュニケーションに対する情熱に満ちた子だった。
生まれて、幼稚園まで滞在した、ニュージャージ州でも、まわりの人々に全く気兼ねなく話しかける子だった。
米国で、ガレージセールをした時のことだった。
米国では、いらないものを、家の庭先に並べて、販売するということが頻繁に行われていた。近所の日本人の家庭と一緒に、庭先露店を広げた時のことだった。
地元の消防署の大男の係官が、難しい顔をして近づいてきた。君たち、きちんと届出はしてるんだろうね。慌てた親たちが、不慣れな英語であたふた応答している時だった。
突然、当時3歳ぐらいの娘が、その大男に笑顔一杯で近づいていき、How are you?と抱きついていったというのだ。
流石の大男も、この不意打ちに、思わず破顔一笑。Fine. Thank you. And you?となったのだ。まわりの緊張もそれを機会に一気にほぐれたのである。
近所のお母さんたちは、一発勝負に強い子よねえと感心しきりだったらしい。
近所のおばあさんや、知らない人に平気で話しかけるという、この種の逸話には、ことかかない。誘拐されないようにと皆が本気で心配したほどだった。
高校三年生になった今も、いろんな人たちと知り合っていきたいという思いは相変わらず強い子だ。
ただ、そういった外向性とシャイなところが微妙なバランスで存在している。これも含めて彼女の個性だと思う。
表現というアウトプットの質を決めるのは、インプットの質と量だ。
日々、表現という作業をする中で、彼女のこれまでの人生の中で蓄積したささやかな蓄えは使いつくされた。毎日、いい絵が描けないと悩んだり、泣いたりしている。
自前のたくわえがなくなり、学校で教わる定型の技法の影響が強まる中で、いったん個性が消える。定石を覚えたての将棋が弱くなるのと同じだ。
ここで、アウトプットの方を一定にしながら、インプットの質と量を上げる方法を獲得することが、表現者としての彼女の挑戦なのだろう。
そういった緊張の中で、手話という新しいインプットの手法を得たということは、何か象徴的だ。
電車の中で、手話で舞うように笑いさざめきあった少年、少女たちの顔がふとよぎった。
母の左手(2005年9月)
台風の影響で、東京でも大雨が降った。
ニュースでは、ハリケーンで、ニューオリンズ全域が都市機能を失ったことの続報が報じられている。
自然は、人間に対して、こうしてメッセージを送り続ける。
総選挙まであと1週間になった。地下鉄の駅前で、民主党のマニフェストを配っている。この選挙で何が変化するのか、それがぼくが生きているということにどんな影響を与えるのかはよくわからない。でも、ぼくは、マニフェストの小冊子を受け取って読んでみようと思った。
雨のたびに、街の空気は、秋へと向かっていく。
関東での初めての夏で、風邪をこじらせて、救急病院へのICUに担ぎ込まれた母親も、ようやく、状態がよくなり、もとの療養型病院の自分の部屋へと戻った。週末ごとに、通うというもとのペースが戻ってきた。
病室で横になっている、母親の顔に元気がなかった。
2週間近く、肺炎間際で、体力を消耗したのだから、仕方がないと言えば、仕方がない。声も小さく、耳を寄せないと聞き取れない。
表情の寂しさがなんとも辛い。
梗塞のため左半身不随になってから、今の療養病院で、リハビリを繰り返し、かなり左手が動くようになっていたのだが、この数週間の寝たきりで、左手はだらんとしている。

妻が言う。
「おかあさんが寂しそうなのは、左手のせいじゃないかしら。」
半身不随になったあと、母には左半身の感覚がなくなったらしく、自分の左手を自分を認識することができなくなっていた。
いつも不思議そうに、これは何かねえ、誰の手かねえと言っていた。
母にとっては、左手は、自分の胸や顔を触ろうとする子供たちのものなのだった。その子供は、小さい頃のぼくであり、孫たちであり、その他、小さくいとおしく、手のかかるものの手だったようなのだ。
母は自分の左手によく話しかけていた。ちゃんと挨拶しなさい、あなたも欲しいだったらはっきりいいなさい。
ぼくたちは、苦笑しながらも、母が一人きりでないことにどこか安堵っとしていた。
母親が小さな声で、「いなくなると、寂しいものだね。」と、悲しそうにいったというのだ。
妻の推理は、また動かなくなった左手とともに、どこかへ消えた子供たちが母の孤独の原因ではないか。
婦長さんが、リハビリは来週からゆっくりと無理のないようにはじめようと思っていますと言う。
細くなった足をさすりながら、母親が、おそらくリハビリの時に行っているのだろう、小さな声で数を数えるのを聞いていた。
リハビリが、左手の動きと、あの手のかかる子供たちを連れ戻してくれればいいと思った。
人間の心は幻想に取り巻かれている。幻想の支えなしには、人間は生きられない。
現実のぼくよりも、今、彼女の想念の中の父や、子供たちが母を支えているのだろう。
時が癒すもの(2005年10月)
時間が経つのは早い。
それは、哀しみであると同時に救いでもある。
父親が急逝してから、8ヶ月が経った。

故郷に帰省した。早めの1周忌を行うためだ。
北国は、
少しずつではあるが、秋から、初冬への装いをみせはじめていた。
Georges Moustaki: "Il est trop tard"
今は、誰も住むもののいない実家に、親戚の叔父、叔母が集まってきた。
本当だったら、夏に、父の生まれ故郷の墓へ、納骨をする予定だった。
ただ、都合があって、それは来年まで延びた。
父の仮住まいは、地元のお寺にしつらえられた、小さな仏壇の中である。
床から、しんしんと寒さが上がってくる、広い本堂に、お経を読む声が響く。父親の遺影は、いつもどおり笑っている。皆が良い写真だと言う。
まだ子供たちが幼かった頃に、父と母、そしてぼくたち夫婦、そして孫たちみなでとった家族写真の中から、選んだ。
ゆったりとした笑顔だ。遺影に使ったあと、葉書版にして、親族へ送った。その中の一枚が、東京の僕の家の居間でも笑っている。
母親は、一周忌の場にはいない。彼女は、東京の療養性病院に入院している。
納骨が延びた事情のことだが、8月の納骨のために、父の故郷の漁村にあるお寺に連絡し、親族郎党の宿泊の段取り等をすべて済ましたある夜のことだった。
母の病院から電話があった。
急変することはないと思うのですが、お母さんちょっと風邪をひいて、その後、痙攣が出ています、脳梗塞の影響かどうかについては、明日の朝にならないと判明しません、大事には及ばないとは思うのですが、医師からの連絡があるかも知れませんのでよろしくという内容だった。
時計は9時を廻っていた。妻と相談したが、家で、待っていても仕方がない、病院へ行こうということになった。
家に帰る通勤客の流れと一緒に、病院へと向かった。
10時過ぎに病院へと着いた。医師は診察中なので、少しお待ちくださいと、病室の近くの、暗く、誰もいない、談話室に座った。看護士の青年がお茶をいれてくれた。
小一時間ほどして、若い当直医が、説明に来た。
今の痙攣が風邪の熱からくるものか、または、再度、脳内出血を起こしたためのものかは、今の段階ではわかりません。
この病院では、明日の9時ぐらいまで、その検査ができないので、その時間を待つか、精密検査を即座にやってくれる、大きな病院へと救急車で連れて行くかを判断してくださいという内容だった。
医療関係に勤めていた義理の叔父に携帯電話で連絡をし、相談した。
万が一ということもあるので、救急車で移送することにしたと、医師に告げると、わかりましたと執務室に戻り、電話をかけはじめた。
考えてみれば、こういった万が一の対応が迅速にできるように、母を東京へ呼んだのだ。そこで優柔不断な判断をしていては、悔いが残ると思った。
若い医師が戻ってきて、近隣でもっとも大きい医療センターの脳外科に移送することにしましたとぼくの眼を見て言った。
母は救急車、ぼくたちは、タクシーでその病院へと向かった。
医療センターへ着くと、直ぐに検査が始まった。
ぼくたちは、救急用入口の近くの狭い待合室で、待った。救急センターでもあるその病院へは、11時を過ぎても、患者や、当直の看護士たちが、ひっきりなしに出入りしている。
1時を過ぎた頃に、担当の医師に呼ばれた。
脳内出血はないので、あと、風邪に伴う、肺炎等のリスクがないようであれば、一日二日ここに入院して、そのあと、従来の病院へ戻ることができると思うという発言だった。
安堵した。
ただ、血液検査等その他検査はすぐには終わらないので、明日の、午後一番で、また来て欲しいということだった。
集中治療室に母を運びこんだあとに、ぼくたちは病院をあとにした。
翌日の医師のトーンは少し違っていた。
脳内出血はないのですが、血液の状況があまり良くありません、肺炎になるリスクを避けるためにも、しばらく入院の必要があります。
そのあと、一拍、間をおいて、40代はじめぐらいに見える脳外科の医師は、こう切り出した。
高齢の人の場合は、容態が急変することがあるので、あらかじめ、家族の方と緊急時にどうするかについての相談が必要になります。
具体的に言うと、肺炎などが急に悪化すると、呼吸が困難になり、そのため、呼吸させるための器具が必要になります。
そういった器具にも限界があり、最終的には喉を開いて、そこに直接器具を繋ぐ必要があります。
しかし、この状態になると、これは通常の治療ではなく、いわゆる延命措置の段階に入ります。器具によって命を永らえている状態です。
そのため、器具を取り外すことが、命の終りを意味することになるわけです。
このため、家族は、精神的に非常に困難な状況に置かれます。
私達は、そういった人工的延命措置をおすすめはしません。ただし、ご家族の意志を尊重しますし、延命措置を選ぶ方々もおられます。
昨日のトーンとの違いに、ぼくはショックを受けた。しばらく、考えさせてくださいと言って、屋外に出た。妻も蒼白な顔をしている。
病院に勤務していた叔父に電話をかけて、内容を説明した。叔父も、ことの急変に驚いていた。ぼくは、延命措置は避けようと思うと言った。
母とそんな話をしたことはなかったが、父親が生前、管だらけで死を迎えるのだけは絶対に嫌だといっていた言葉を思い出した。
叔父も、少し黙ってから、それが良いと思うといった。
義理の叔父は、妻の長兄である、ぼくの父親を、近くで長年見守ってくれていた。ぼくも、高校時代に下宿したこともある、親戚の中で、もっとも親しい一人だった。
海外出張、東京勤務と、故郷にいない、ぼくに代わって、両親を見守ってくれていた彼の意見は、ぼくには重かった。
ナースセンターへ戻り、担当医に、その旨伝えた。
脳外科医は、ぼくの眼を見て、わかりましたと一言言った。
それから、3週間余り、母は、この集中治療室で戦った。ぼくたちは、そのまわりで、ただ見守るだけだった。幸い、母親の生命力は強く、いろいろな数値が改善し、彼女は、元の療養性病院へと戻ることになった。ただ、こういった事情で、予定していた納骨のための帰省は見送りになった。最愛の妻の生命を父が優先するのは明らかだったからだ。
元の病院の看護士の人達のおかえりなさいという笑顔に迎えられ、彼女のリハビリがまた始まっている。
今回の入退院の前には、かなり回復して、動いていた彼女の左手は、残念ながら、またもとの状態に戻り、動かなくなっていた。動きはじめた手を、母は、自分の手とは認識せず、自分の孫たちの手だと思いこんでいた。やっかいな存在でありながら、彼女の孤独感を癒す存在でもあった。
かなり安定し、元通りの会話の状態に戻ってきたある日、母は、寂しいのよと言った。必ずしも要領を得ない会話の内容を総合すると、左手に宿っていた子供はどこかにいなくなってしまったらしいのである。左手の動きがなくなると同時に、騒々しい子供たちもどこかへ消えてしまったのだ。これは、ぼくにもショックだった。自分の身体としては意識できない左手が、人の心を癒すという不思議さに、ぼくたちも救われていたからだ。
左手の動きが戻れば、またあの騒々しい子供たちが、母のもとに戻ってきてくれるではないかというのがぼくの今の最大の希望だ。
お寺を出て、会食先のホテルへ向かう車の中で、叔母がぽつりと言った。
母さんは、父さんにお墓の中に入って欲しくなかったのかも知れないね、もう少し、自分の側にいて、助けてよって言ったのかも知れないねと笑った。
久しぶりに帰ってきた実家でも、ぼくは、何も感じない。
父親の気配は、一つの場所に固定されず、世界に遍在している。
病院でも、相変わらず、母親は、今、お父さん出て行ったばかりと、夫の存在を疑わない。
ぼくは、それを認知症のせいと、割り切ることもできない。オカルト的な意味ではないのだが、父は、ぼくたちのそばに存在している。
一番単純に愛された孫である中学3年の息子は、おじいちゃんがいなくなったという気がしない言う。たしかに、それが家族の実感である。
母親の、お父さんとさっき話したらという言葉の中で、ぼくたちは、父親と、家族という物語を反復している。
一周忌は終わった。
来年、暖かくなったら、その先のことを考えようと思っている。
父親が急逝し、母親を故郷から東京へと連れて行く過程で、家族、親族、知人の間で、それなりの緊張があった。緊張の度合いは、激しくはないが、その静けさと穏やかさの故に、その当事者であるぼくたちの精神には深くこたえた。
しかし、やはり時間が癒す部分というのは大きい。
一周忌のあとの会席の場で、皆の顔は優しい。父親の思い出を、やさしい顔で語り合っているし、老いた兄弟たちが、思い出を語り合えることの幸福をかみしているようだ。
いずれにせよ、死ぬ間際まで、妻の病院への見舞いを続けた父親は、最愛の妻が望むことを望むはずだ。
深く考える必要などはない。時間がすべてを決め、すべてを癒していくはずだ。ぼくたちは、その流れに従うだけだ。
神楽坂ルクロモンマルトルはいつものように2007年4月
JRの飯田橋の駅を出ると、ひんやりとした花冷えのような黄昏が広がった。カナルカフェのある濠のまわりの外堀通り沿いの桜が満開で、そぞろ歩きの人の数も多い。もともと人気のある場所だった、神楽坂が、ついこないだ最終回を迎えた倉本聡の人気テレビ番組の影響もあって、休日とはいえ、観光客でにぎわっている。

千葉の病院に入院している母親を、義理の妹たち(つまりぼくの叔母たち)が見舞った帰りに、皆で、神楽坂へ戻ってきて、いつものようにルクロモンマルトルで夕食をした。
予約の時間には少々はやめだったので、カナルカフェの周辺の桜を見たり、神楽坂沿いの、小間物屋や、手作り靴の店や、お香の店などを皆でぶらぶらして、時間をつぶした。

春といっても、夕方となると、まだまだ風は冷たい。
神楽坂を下って、コンビニの角を曲がり、パチンコ屋の前を通って、路地を折れたところにルクロはある。もう何年になるだろう。週末に散策していて、偶然入り、その気の置けない雰囲気が気に入り、足繁く通っている。繊細というよりは、味の輪郭のはっきりとした料理のよさもあるが、日本の大手ホテルの元ソムリエだったらしい、フランス人のオーナーの過度に踏みこまない、何気ない接客が好きだ。家族だけではなく、仕事仲間も連れてくるようになったが、皆、雰囲気や料理を喜んでくれる。
オーナーはいつもどおり、表情をあまり変えるでもなく、歓待の意を呈している。
夕方最初の客なので、まだ、店内はまばらだ。食前酒のシャンパンを飲んでいると、予約なしのお客が何組かやってきたが、さすがに土曜だけあって、予約で一杯のようだ。前から週末は当日の予約は難しくなっている。
オーナーが、カスレは今週で最後だよと声をかけてくる。カスレというのは、豆や、ソーセージや肉のたっぷりと入った田舎風シチューで、中くらいの壷のような器に入っている。最初に、食べたときに、気に入って、何度か注文したら、カスレ好きの客ということになったようで、オーナーも、店の人からも、そろそろ、カスレの季節ですよとか、もうすぐ、カスレは終りですよと言われるようになった。
いきつけで、メニューもほぼすべて試してはいるが、今日は、格別、カスレという気分でもなかったが、今年の秋までないとなれば、ということで、結局、カスレを注文した。アントレは、鶏砂肝のコンフィのサラダ。叔母たちや、ぼくの家族たちも、おもいおもいのお気に入りを注文している。子供たちは、この店のキッシュが好物だ。叔母たちはマグロのタルタルサラダやレンズ豆のサラダ。メインは鯛のポワレ、ホタテのソテー、鶏、牛とさまざまである。
赤ワインは、おじさん(家では、この店、ひそかにフランスおじさんの店と呼んでいる)に、何がいいといつものように聞く。まったくワイン通ではなく、飲んだワインを記憶するという習慣もないので、毎回、赤でしっかりとしたのとか、きわめて、大雑把に注文し、おじさんも、それだったらこれときわめて断定的に決めてくれる。それがいい。
以前、ワイン通らしい、若い仕事仲間を連れてきたとき、彼が選んだ高めのワインに、おじさんは、それだったら、この値段のワインで十分だよと、すすめたこともある。そんな、商売っ気のあるのかないのかわからないところが好きで通っている。長期戦略的には、きわめて賢明な戦略なのかもしれない。
以前「調理場という戦場」というベストセラーを書いた、三田のコートドールのオーナーシェフの斉須政雄さんが、幻冬舎新書の新刊で「少数精鋭の組織論」という本を出した。早速、読んでみた。自立するには、近道はないし、知らない方がいいという彼の持論がまた繰り返されている。
器用な人間には続かないのが、料理人だという考え方である。
「近道があると、人はかならず近道を選んでしまいます。しかし、器用に修得した能力だけが能力ではないのです。まわり道をした人だけが宿している何かがあり、それこそが生き抜く術になるのです。(中略)
(料理の世界は)、実際にやることは地味な作業の蓄積です。朝から晩まで手仕事で、誤解を招くかもしれませんが多くの富を得られるような職業ではありません。だからぼくは「食っていければそれでいい」と思います。
儲けに邁進するとギズギズしますし、非効率的だから価値を生み出せる職業です。」
成功すると、すぐ他店舗展開というようなビジネスの論理と、料理の論理とは必ずどこかで乖離が生じるというのは、ビジネスの勉強をしなくても、注意深いお客ならばすぐにでも気づくことである。斉須さんの、生き延びてきた料理人の友人たちを語るこんな部分に、料理というものの、レストランというものの生理がよく説明されている。
「慢心もない。商魂もない。表裏もない。これは自立して15年20年と最前線にいる友人たちの共通点です。友人たちは、信じている価値を、身ひとつでしぼりだしているような生き方でお店を続けています。開店や解雇の修羅場も、恵まれない時もくぐりぬけて満身創痍ですから、それぞれその人にしかにない変な持ち味を宿しているのです。理屈や上手下手ではない、生理がこめられた、また食べたくなる料理が出てくる。」
そんなに食通でもないし、食通という存在に対する、心理的反発もどこかであるので、そんな見方でレストランに対してきたことはないが、少なくとも、自分がくりかえし行く店にはまぎれもない共通点がある。お客の側から見たら、いきつけになるレストランというのはシンプルなものである。切れ味の良い料理だけが残っていくのではない。
「性格、野心、交友関係・・・料理人が転ぶ要素はいくらでもあります。バランスのよくない生き方は危険です。「強い個性」を出すのは簡単ですが、なぜそれが続かないかを考えなければ・・・そこに生き残る理由があるのだし。大事なことは、愛される料理であるかどうかで、お客さんに愛されていない料理は埋もれて飽きられて消えてゆく。それが大半の料理の運命です。」
料理も他の仕事にも共通することがある。最後は、その人間のすべてが問われるということだ。だからこそ、奇策に走る必要もなく、自分のリズムで自分のやり方で近道をあえて選ばないという「無様でありのままの生き方」でいいのだ。
越路吹雪 モンマルトルの丘 1955 / Complainte De La Butte
定番のデザート、ガトーショコラ、チーズケーキなどをそれぞれが楽しげに選ぶのを観ながら、そんなことを考えていた。
ぴあの(2005年6月)
交通事故でジャズ奏者の父親をなくして、ジャズピアニストの母親と二人暮らしの片腕の少年と、ある夏、めぐりあう気の強い美少女とその弟の話である。交通事故で片腕をなくした少年のピアノと、美貌の母親とそのピアノに対する想いをめぐる物語だ。物語の背後にはいつもジャズピアノが低く響いている。
音楽をめぐる物語が好きだ。昔から音楽が好きだったからだろう。
母親の音楽への愛情と果たせなかった夢への代償のように、はじめたピアノ。父親は喜ばなかった。1960年代という時代が、男がピアノを弾くということに対して持っていた違和感が、父親の反応に反映していた。中学ごろまでは音楽大学をそれなりに、真剣に考えていた節がある。ただ小学校の高学年の頃から入り込んできたギターという楽器が、ぼくの音楽生活をどんどん趣味の方向へと変えていった。
ジャズに対する畏敬が生まれてきたのはいつ頃だったろう。
北国の古い港町で小学校に行っていた頃、父親が書斎の半分を占めるような大きなステレオを買ってきた。その後ベストアルバムをよく買ってきた。ブラザースフォア、ジョーン・バエズ、そしてマイルス・ディビス。そのあたりに発端はありそうだが、中学の頃から若干ませ気味に読みはじめていた五木寛之の小説の影響もあるだろう。「青年は荒野をめざす」「デラシネの歌」「内灘夫人」などには、まぎれもなくジャズの音が響いていた。
ジャズをめぐる記憶を手繰っていって次にいきあたる光景は、1970年代前半の古い貿易港だ。ぼくはこの街のプロテスタント系の私立高校に通う17歳だった。ぼくはバリトンの声をかわれて、グリークラブに入団していた。男声合唱の分野ではそれなりに知られた伝統のあるクラブだった。

そのクラブのスノビッシュな雰囲気が、当時庄司薫の青春小説に展開される、高校生活に憧憬の念を抱いているような少年を集めるようになっていて、一種独特の、高校というよりは私立大学のような雰囲気があった。ぼくのジャズをめぐる記憶は、クラブの合宿だ。毎年、全国大会をめざし、まるで体育会的にストイックな練習を続けていて、冬休みには恒例の冬合宿があった。高台にある元外国の領事館の建物で、昔はその国の領事がジャム入りの紅茶でも飲みながら、窓の外に広がる港の風景に見とれていたダイニングルーム跡のホールの片隅に、古ぼけたレコードプレーヤーがあった。
ぼくの一級上にMという大人びた少年がいた。Mの兄貴もこの高校の卒業生だった。彼は、ジャズフェスティバルなどが開催されている洒落た街の中学の出身だった。Mの兄は大学を卒業した後、プロのジャズピアニストになり、新宿のピットインなどで演奏するようになっていた。
Mが大事そうに一枚のレコードを取り出して、プレーヤーにのせ、針を落とした。数人の少年は文字通り息をつめて、まるで、聖なる儀式をみつめる信者の風情で、天上の音の到来をまちわびていた。これまで聞いたジャズの音の塊とは違った、リリカルなピアノの響きがそこにはあった。Mが持っているカバーにはチック・コリアという名前が印刷されていた。ホールの暗い照明のしたで、石油ストーブの紅い炎に包まれ、皆あたりを気遣うように小声で話しながら、その新しい音の連なりにひたっていた。
Return To Forever (Chick Corea, Stanley Clarke, Al Di Meola, Lenny White) - Jazzaldia Festival 2008
次の光景は、1970年代の東北の大都市へ移る。ぼくは20代の大学生だ。少年の頃の音楽大学は、現実という中でなし崩し的に消えていき、当然自分の中にも音楽と心中するというものがあったわけでもなく、さしたる断念もなく法学部という見事に現実的衣装を身にまとうようになっていた。法律という現実と20代という情緒とのあいだでかぎりなく不安定だった。そんなギャップを埋めたのがジャズだった。
一番町という繁華街の一本路地に入ったところに、その小さなジャズ喫茶があった。カウントという看板がかかっていた。中国人のようなマスターと職人風の若い男が、切り盛りしている店だった。ファッション化して、そのうちにアイデンティティがなくなって潰れてしまった東京のジャズ喫茶とは違って、徹頭徹尾、地下室的な意固地さが蔓延している空間だった。ただ客層は学生ばかりじゃなかった。

店に備え付けの落書き帖には果し合いのようなジャズ評論が書きなぐられていた。自分が何かを書いたあとに、誰かがそのノートを読みはじめるときの胸騒ぎのような気持ちは、いまでも忘れられない。ぼくはそこに通いつめて、ジャズファンというものの、行儀作法の一式を教わった。ソニー・クリスのクリスクラフトというぼくにとっての名盤にであったのもこの店だった。薄暗いカウンターでコーヒー一杯でねばりながら、文庫本を読むなどという昔なつかしい大学生を演じさせてもらった。倉橋由美子の「暗い旅」を読んだのも、この店のカウンターだったし、その中にでていた京都のシアンクレールというジャズ喫茶めあての旅を、することにもなった。
ピアノとジャズをめぐる記憶はここから、一足とびにに90年代のニューヨークに飛ぶ。ぼくは30代後半の二人の子持ちの金融マンだった。ニューヨークとはいってもブルーノートとか、スイートベージルのおもいでじゃない。ラジオをひねると一日中ジャズが流れている局があったり、映画のBGMにもジャズが多い。ジャズはニューヨークの空気の中にみちている。しかしぼくのニューヨーク的ジャズの記憶はそこにはない。
妻が突然ピアノをはじめたいと言いだした。
ぼくたちの住んでいた街には、同じような環境の駐在員が多かった。学歴も境遇もきわめて似通った人種が集まっている。彼らは似たような少年少女時代をおくって、似たような青年時代をおくり、これまた似たような断念をして、この異郷にいる。そんな類似した境遇の中でも、ピアノをめぐる思い出を共有する人々は意外に多かった。

皆どこかでピアノをはじめ、一度は音楽大学を目指し、同じく軽い断念とともに、ピアノを捨てている。そして社会の中でそれなりに努力し十数年働き、あるいは家事に没頭し、ふっと自分というものをふりかえるときに、断念の軽さのゆえに、ピアノをめぐる記憶が奔出するようなのだ。いわば、ピアノというものが自分がありえたかもしれない素敵なもの、心踊るすべてのものを、集約的にあらわすとでもいうかのように、ピアノへの想いが強まるのだ。
日本人が教えるピアノスクールに、妻は隣人たちと通うようになった。ロバート・ペースという教師が作った、Cという特定の音階中心主義を相対化する試みだった。それと同時に、古典音楽を時系列的に辿るのではなく、存在する音楽を横に並列して、現代音楽と古典音楽が共存している。ヘンデルとバルトークやさらに現代的な音楽家の作品が、ひとつの練習曲集に並存している。戯れに弾いてみた曲想の新しさにぼくの中でも、かつてありえたかも知れない自分が、ピアノという形で甦ってきた。そしてぼくも土曜の午後に子供や主婦にまじって、ジュリアードに通っている若い教師から、ピアノレッスンを受けることになった。
ぼくは練習曲として、ドビュッシーのベルがマスク組曲の序曲をもらった。まるで音楽大学というコトバがそれなりに重大な響きを持っていた中学生や、モダンジャズという秘教めいた響きに憧れた高校生の、ぼくが帰ってきたようだった。練習がすすむにつれてぼくはわがままをいい、ビル・エバンスの採録譜を買ってきて、ワルツ・フォー・デビーの練習を始めた。ハドソン川沿いの町で、若いピアノ教師の視線に晒されて練習したビル・エバンスがぼくにとってのもっともニューヨーク的なピアノの記憶だ。
ピアノの天性を持ちながら、事故という形でその天命の宿る片腕を失った少年と、彼の右手が奏でるサマータイムのメロディーに、運命的に吸い寄せられる姉弟の物語は、ぼくの中でガーシュインの旋律を基調低音として、散乱していた記憶の破片をひとつづきの物語の形によせあつめた。ぼくや、ぼくと同じ時代を生きてきた多くの普通の人々のありえたかも知れない自分とその断念、あるいは失われた片腕へのかすかな後悔と郷愁がピアノというコトバに集約される形で僕の物語を呼び寄せた。